人口増加による代償
気分転換に展示会のカタログを一気に見ていると、当時と違った視点で見られて面白かった。
特に気になったのは、「ロスト・ヒューマン」展のもの。
各職業の目線で、これまでの人類の発展とその行く末のメッセージが、写真とともに掲載されている。
その中でも人口増加や性についてのものが目についた。女性が優位に立ち、男性がラブドールに性のはけ口を求めたことで、人類が存続しなくなったという結末だったり、ヒトゲノムの発達によって、病気や死期が分かり文明が発達しなくなったり、避妊の意識欠如や失敗により、人口が爆発的に増加してしまい、人の生殖能力が低下したなど。
どれもリアルに、起こりうる未来でゾッとする内容。起こりうるからこそのリアルさでもあるので、どのメッセージも考えさせられた。生物界において、弱肉強食だったり、環境適応だったりで、生き抜く力が適している生物が現在まで生き残っているわけだけど、人類の場合はどうなのだろうと思う。
人が食べられるような事故も多くはないし、人口に制限はかかっていないゆえに、確かにどこまでも人口を増加させてしまうことが出来そうだ。地球が耐えうる人口とは一体どれくらいなのだろう?
そんな最近、タンパク質の確保が難しい内容をよく目にする。それも人口増加による問題らしい。
食の選択肢
日本では人口減少だけれど、世界的には人口が増加している。世界単位でもそうだけど、地球の歴史単位にまで目を向けると、人類はひたすら作り出す作業をしてきたかもしれない。文明や経済、そして人口。
よりよくしようと、色々な発達を起こしてきた人類。それは良いことでもあるし、地球的にはよくないことももちろんあったと思われる。
「サスティナブル」という言葉も目にすることが多くなった気がするが、そろそろ考え始めないといけない時期なのだろう。
ふと、録画していたイッテQの番組で、マラウイ共和国の定番フード、ユスリカバーグを観て、今回のたんぱく質ネタに結びついた。他にも、貴重なたんぱく源を確保するため、虫は結構出てくる。我々普通の日本人には馴染みがないが、昔はイナゴの甘露煮など食べていた。経験の差だけかと。
マラウイ共和国の生活を見ると、ゴム跳びだったりコマ回しだったり、昔の日本の生活と似ているところがあるらしい。今やそういう遊びはなくなったが、そういった自然に近い生活スタイルは、国が違えど共通していることからも、人が求める基本的欲求を満たすものなんじゃないかとも思った。
そんなイナゴの缶詰、売っているらしい。かなり前に衝撃だったので、今も忘れない吉祥寺の自販機。
別の所に、サソリとかも取り扱いがあるところもあるようだけど、本当に必要な時に備えて、もう少し扱いやすいようにしていただければな、と勝手に思う笑。やはり見た目の壁は大きいので、ミンチだったり、粉末だったり、少し加工をしていただければ、意外と取り組めるかもしれない。


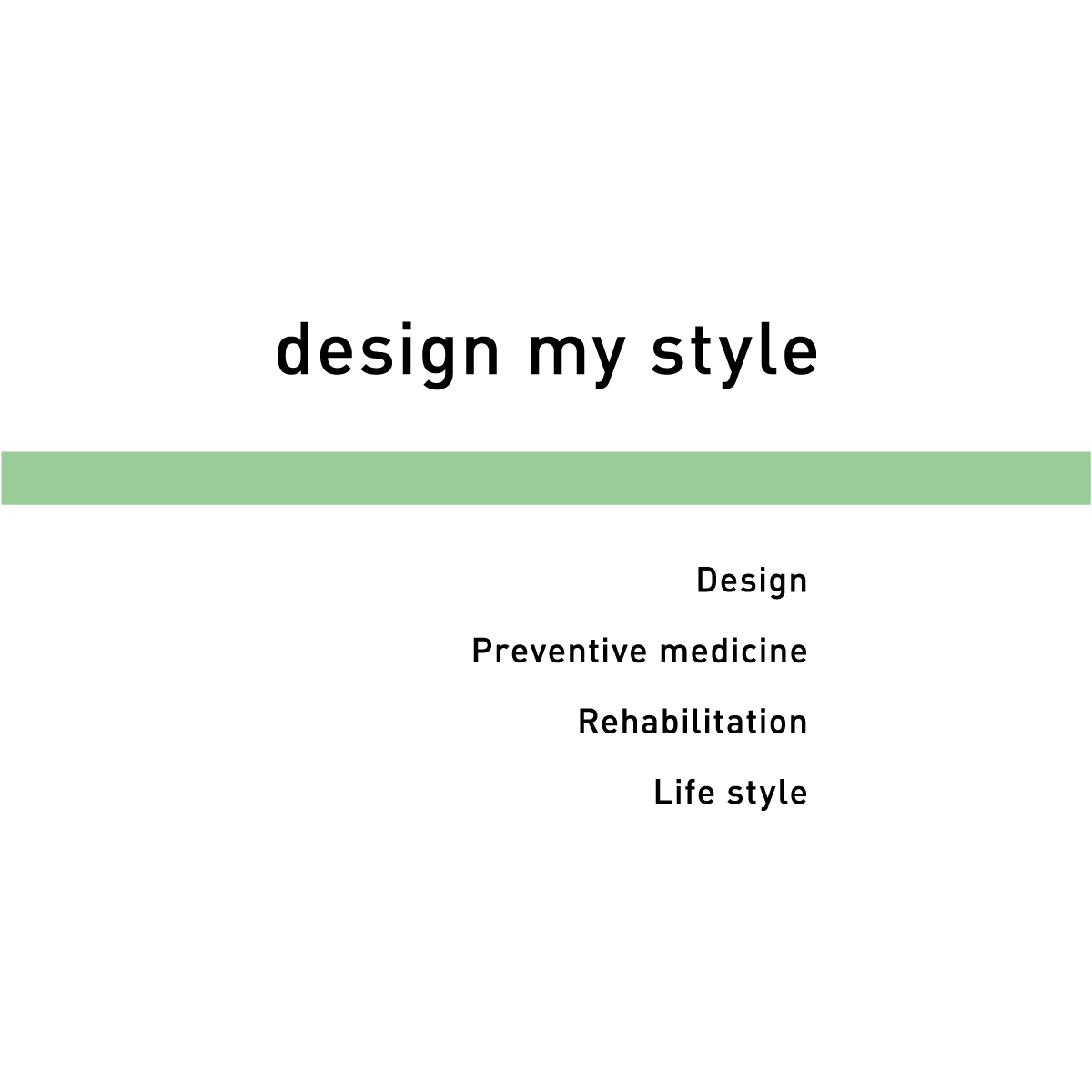

Comment